
切削油剤が原因で発生する悪臭に困っていませんか。
この記事は切削油剤メーカーであるサンワケミカル株式会社に記事執筆を依頼し、切削工具と切削加工業界に特化した専門サイト「タクミセンパイ」が編集しました。
本記事では切削油剤が原因で発生する悪臭の原因と対策についてまとめています。
この記事を読むことで、切削加工の現場における悪臭の困りごとについて、原因を把握した上で適切な対策を講じることができます。
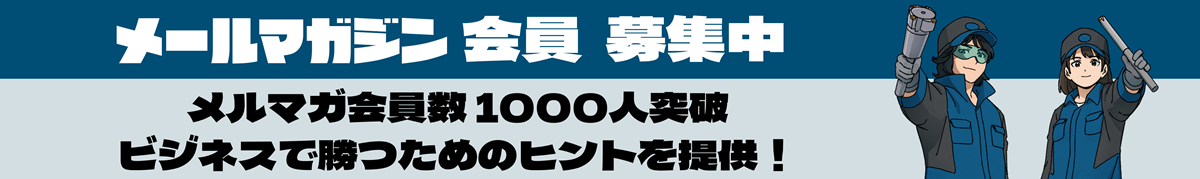
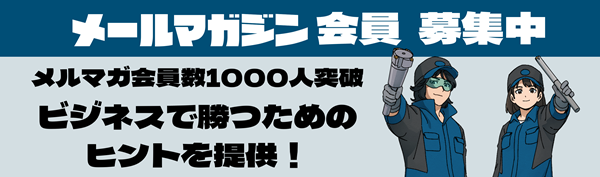
切削油剤が原因で発生する悪臭の原因と対策
本記事では、切削油剤が原因となる悪臭問題の原因と対策について下記をまとめています。
- 切削油剤の悪臭が作業環境と効率に与える深刻な影響
- 切削油剤が関係する悪臭の発生原因
- 切削油剤が原因で発生する悪臭の測定方法
- 切削油剤が原因で発生する悪臭を根本から断つための対策
- 対策1.腐敗しにくい切削油剤の選定
- 対策2.切削油剤の適切な日常管理
- 対策3.切削油剤のろ過による改善
- 対策4.環境整備と適切な薬剤使用
- 切削油剤が原因となる悪臭の除去方法
切削油剤の悪臭が作業環境と効率に与える深刻な影響

切削油剤が原因で発生する悪臭が、働く環境や作業効率に具体的にどのような影響を与えるのかをまずは説明します。
水溶性切削油剤の腐敗劣化などにより発生する悪臭は、作業環境を著しく悪化させる代表的な要因の一つです。
悪臭の強い環境下では作業者の集中力低下や作業ミスの増加が懸念され、長期間にわたって作業すると、呼吸器系の不調や頭痛などの健康問題を訴える従業員が増加する傾向が見られます。
また、一度付着した臭いはなかなか取れず、通勤時の車内や家庭に持ち帰ってしまうという厄介な問題も引き起こします。
臭いに関する問題は、従業員のストレスだけでなく、企業全体のイメージダウンに繋がってしまう可能性があります。
法的な観点からも、悪臭問題は無視できません。
悪臭防止法では、工場などから発生する不快な臭いに対して規制が設けられており、近隣住民からの苦情が発生した場合には、行政指導や改善命令、最悪の場合は操業停止に至る可能性も否定できません。
そのため、適切な悪臭対策を講じることは、コンプライアンス遵守の観点からも極めて重要です。
切削油剤が関係する悪臭の発生原因

切削油剤由来の悪臭に対して効果的な対策を講じるためには、種類と原因を正確に把握する必要があります。
切削油剤の悪臭にはいくつかの種類があり、それぞれ発生原因が異なります。
切削油剤が関係する悪臭の代表的な発生原因を紹介します。
混入油が原因の油性異臭
機械の摺動面油、スピンドル油、防錆油、あるいは前工程で使用された油などがタンク内の切削油剤に混入・乳化することで異臭が発生します。
「油性異臭」などと呼びます。
例えば、代表的な摺動面油である「バクトラオイルNo.2」などは、それ自体も特有の臭いを持っていますが、水溶性切削油剤と混ざることで独特の不快な臭いに変化することがあります。
油性異臭は、油特有のツンと鼻につく臭いで、機械周りに広がりやすいのが特徴です。
混入油は切削油剤の性能を低下させるだけでなく、後述する微生物の栄養源となり、腐敗を加速させる大きな原因ともなります。
微生物の繁殖による腐敗臭
水溶性切削油剤で最も問題となるのが、微生物(バクテリアやカビなど)の繁殖とそれに伴う腐敗によって発生する悪臭です。
「腐敗臭」などと呼びます。
切削油剤には鉱物油、脂肪、界面活性剤など、微生物にとって栄養源となる成分が含まれています。
これら切削油剤中の栄養源と、加工時に混入する切粉や機械の潤滑油、さらには工場内の空気中に浮遊している微生物などが結びつくことで繁殖しやすい環境が生まれてしまいます。
特に、タンク内の切削油剤に嫌気性細菌が増殖すると、その代謝物として硫化水素(温泉地などで感じる卵が腐ったような臭い)やメルカプタン類(玉ねぎが腐ったような、あるいは都市ガスに付臭されている臭い)などの強烈な悪臭ガスを発生させます。
また、切削油剤のタイプによっても腐敗のしやすさは異なります。
一般的に、鉱物油や油脂類、界面活性剤を多く含むエマルジョンタイプの切削油剤は、微生物の栄養源が豊富なため、ソリュブルタイプやシンセティック(ソリューション)タイプと比較して腐敗しやすい傾向にあります。
切削油剤に含まれるアルカリ成分が原因のアルカリ臭(アンモニア臭)
水溶性切削油剤には防錆やpH調整のためにアルカリ成分が含まれており、この成分が原因でアンモニアに似た特有の刺激臭が発生することがあります。
「アルカリ臭」や「アンモニア臭」などと呼びます。
水溶性切削油剤のアルカリ成分が原因で発生する悪臭は、気温や液温が高くなる夏場に強く感じられる傾向があります。
切削油剤が原因で発生する悪臭の測定方法

切削油剤が原因で発生する悪臭の強さは単なる主観的な感覚だけでなく、客観的な指標で評価・測定することも可能です。
悪臭防止法では、特定悪臭物質として22物質が指定されており、それぞれ敷地境界線や排出口での濃度規制値が定められています。
例えば、代表的な腐敗臭の原因である硫化水素の規制基準値は、地域の状況や排出基準によって異なりますが、一般的には0.02~0.2ppmの範囲で設定されています。
硫化水素はおおよそ0.0005~0.025ppm程度で人間が臭いを感じ始め、2ppmを超えると目や呼吸器への刺激が現れることがあるとされています。
代表的な悪臭の測定方法を紹介します。
官能検査(嗅覚測定法)
官能検査(嗅覚測定法)は、複数の訓練された検査員が実際に臭いを嗅ぎ、その臭気強度を所定の尺度(例:0~5の6段階臭気強度表示法)で評価する方法です。
検知管式ガス測定器
検知管式ガス測定器は、硫化水素やアンモニアなど、特定の悪臭物質の濃度を現場で簡易的に測定できる器具です。
ガラス管内に充填された検知剤が対象ガスと反応して変色し、その変色長からガス濃度を読み取ります。
ガスクロマトグラフィー・質量分析法
ガスクロマトグラフィー(GC)・質量分析法(GC/MS)は、悪臭の原因となる揮発性有機化合物などをより詳細に特定し、その濃度を精密に定量分析できる高度な分析手法です。
切削油剤が原因で発生する悪臭を根本から断つための対策

切削油剤が原因で発生する悪臭を効果的に防ぎ、快適な作業環境を実現するためには、1つの対策に頼るのではなく多角的なアプローチが必要です。
切削油剤が原因で発生する悪臭に対して有効な下記4つの対策方法を紹介します。
- 対策1.腐敗しにくい切削油剤の選定
- 対策2.切削油剤の適切な日常管理
- 対策3.切削油剤のろ過による改善
- 対策4.環境整備と適切な薬剤使用
対策1.腐敗しにくい切削油剤の選定
悪臭対策の最も効果的な方法は、腐敗しにくく、悪臭が発生しにくい切削油剤を選定することです。
切削油剤タイプの検討
一般的に鉱物油を主成分としないシンセティック(ソリューション)タイプの切削油剤は、エマルジョンタイプやソリュブルタイプと比較して微生物の栄養源となる有機物が少ないため、腐敗しにくいとされています。
ただし、加工の種類や材質によっては潤滑性や防錆性、洗浄性といった他の性能も重要となるため、必要な性能とのバランスを総合的に考慮して切削油剤を選定する必要があります。
防腐性能・抗菌性能に優れた切削油剤の選定
多くの切削油剤メーカーが、防腐性能や抗菌性能を高めた製品を開発・提供しています。
しかし、強力な殺菌力を謳う切削油剤の中には、PRTR法に該当するような人体への刺激や環境負荷が懸念される防腐剤や殺菌剤を多量に含んでいるものもあり、作業者の安全衛生面で課題があるため注意が必要です。
対策2.切削油剤の適切な日常管理
どんなに優れた切削油剤を選定しても、その後の管理が不適切であれば、性能を十分に発揮できず、早期の腐敗や悪臭発生に繋がってしまいます。
悪臭防止のためには、日常的な切削油剤の管理を徹底することが極めて重要です。
切削油剤の適切な日常管理について紹介します。
切削油剤の濃度管理
切削油剤の濃度は、その性能を維持するための最も基本的な管理項目です。
切削油剤の濃度がメーカー推奨値よりも低すぎると、防腐性能やpH調整能力、潤滑性などが低下し、微生物が繁殖しやすくなったり、加工不良が発生する原因となります。
定期的に屈折計や滴定法で切削油剤の濃度を測定し、常に適正な濃度範囲(例:5~10%など、油剤の種類や加工条件により異なります)を維持するため、希釈水の補給だけでなく原液の補給も適切に行いましょう。
切削油剤のpH管理
多くの水溶性切削油剤は、アルカリ性に調整されることで細菌の増殖を抑制する効果を持たせています(一般的にpH8.5~9.5程度)。
切削油剤を使用し続けると、二酸化炭素の吸収や微生物の活動によりpHが徐々に低下し、細菌が活動しやすい中性域に近づくことで腐敗が進行しやすくなります。
定期的にpHメーターやpH試験紙で切削油剤を測定し、初期値から大きく低下した場合(例:1.0以上低下)は、必要に応じてpH調整剤を使用するなどして適正な範囲を維持します。
ただし、pH調整剤の過度な使用は切削油剤のバランスを崩す可能性もあるため、メーカーの指示に従うことが重要です。
浮上油・異物の計画的な除去
機械の摺動面油や作動油、外部から混入する切粉やゴミなどは、微生物の栄養源となります。
また、タンク内の切削油剤表面を油膜が覆ってしまうと、液中の酸素供給が絶たれ、嫌気性細菌の格好の繁殖場所となります。
そのため、浮上油・異物が原因で強烈な腐敗臭が切削油剤から発生しやすくなります。
浮上油や沈殿スラッジを計画的に切削油剤から除去するためには「オイルスキマーの活用」や「定期的なタンク清掃」が有効です。
オイルスキマーの活用
ベルト式、ディスク式、チューブ式など、様々なタイプのオイルスキマーがあります。
タンクの大きさや形状、浮上油の種類や量に応じて適切なタイプを選定し、稼働時間中は常時運転するのが理想的です。
少なくとも、切削油剤の表面が5%以上油膜で覆われたら即時回収が必要と考えましょう。
定期的なタンク清掃
オイルスキマーでは除去しきれない切削油剤内の微細なスラッジや沈殿物は、タンクの底に堆積して微生物の温床となります。
そのため、タンクの底に堆積したスラッジや沈殿物は、更液時に徹底的に除去する必要があります。
分離性能の高いオイルスキマーやシステムを使用することで、廃油量を削減し、処理コストの低減にも繋げることができます。
回収した浮上油や廃液は、産業廃棄物として法令に従い適切に処理する必要があります。
切削油剤の液温管理
一般的に微生物は20℃~40℃程度の温度で最も活発に繁殖します。
夏場や連続加工・高負荷加工により切削油剤の液温が上昇しやすい時は注意が必要です。
クーラントチラー(冷却装置)を導入して切削油剤の液温を適切に管理したり、発熱の少ない加工条件に見直すことで腐敗を抑制することができます。
定期的な切削油剤の更液とタンク清掃
切削油剤は消耗品であり、長期間使用すれば必ず性能が劣化し、いずれは交換(更液)が必要になります。
一般的な切削油剤の更液頻度としては、年に2~3回程度をオススメします。
特に、微生物が繁殖して腐敗が進行しやすい梅雨時期や夏場(6月~8月頃)に計画的に更液とタンク清掃を行うことで、年間通して切削油剤を良好な状態で管理することができます。
更液の目的は、単に新しい切削油剤に入れ替えることだけではありません。
タンクの奥底や壁面、配管内部などに付着・堆積した金属スラッジ、微生物の死骸やバイオフィルム(微生物の集合体)は、新たな腐敗の温床となります。
そのため、更液で最も重要なのは、タンク内を徹底的に清浄化することです。
いくら頻繁に新しい切削油剤に交換しても、汚染物質がタンク内に残った状態ではすぐに微生物に汚染されて早期に劣化・腐敗し、本来の性能を発揮できません。
更液タイミングの判断基準
切削油剤の更液タイミングは使用期間だけでなく、以下のような液の状態を示す指標を確認して総合的に判断するとよいでしょう。
- pH値の低下:初期値から1.0以上低下した場合(例:pH9.2 → pH8.0など)
- 細菌数(一般生菌数):10⁶ CFU/mL (コロニー形成単位/ミリリットル) 以上になった場合
- 臭気の明らかな悪化:明らかな腐敗臭(硫化水素臭やメルカプタン臭)が発生した場合
- 外観の著しい変化:液の濁りがひどい、油剤成分の分離、著しい変色などが見られた場合
- 切削性能の低下:工具寿命の短縮、加工面粗さの悪化、防錆不良などが見られた場合
対策3.切削油剤のろ過による改善
切削油剤中に浮遊・沈殿する微細な切粉、砥石の砥粒、外部から混入する微細なゴミ、微生物の死骸やそれらが凝集した塊などが劣化を促進させて悪臭の原因となります。
これらの微細な汚染物質を効果的に除去するために、適切なろ過装置を導入・運用することは悪臭対策として有効な手段です。
浮上油を除去するオイルスキマーとは異なり、ろ過装置は液中に分散した固形物をターゲットにします。
加工内容(材質、加工精度、切り屑の量や種類など)、使用している切削油剤の種類、タンク容量、設置スペースなどを総合的に考慮して適切にろ過装置を選定・運用することで、切削油剤の清浄度を高く保ち、腐敗の進行を大幅に遅らせて悪臭の発生を効果的に抑制することができます。
主なろ過装置には以下のような種類があります。
マグネットセパレーター(磁気分離装置)
強力な磁石を用いて、切削油剤中の鉄系の切粉や微細な鉄粉を効率的に吸着・除去します。
構造がシンプルでメンテナンスも比較的容易です。
サイクロンフィルター(遠心分離式液体サイクロン)
ポンプで圧送された切削油剤をサイクロン内で旋回させ、その遠心力を利用して、油剤よりも比重の大きな固形物(切粉、スラッジなど)を分離・除去します。
フィルターメディアを使用しないため、消耗品の交換が不要なタイプもあります。
比較的細かい粒子まで除去可能です。
ペーパーフィルター / カートリッジフィルター
ろ紙や糸巻き状・プリーツ状のカートリッジフィルターを物理的な障壁として、切削油剤を通過させることで、微細な固形粒子を捕捉します。
ろ過精度が高い反面、ろ材が目詰まりするため、定期的な交換や清掃が必要です。
遠心分離機(クーラントセパレーター)
高速回転するローターによって強力な遠心力を発生させ、油剤中の微細なスラッジや、水よりも比重の軽い混入油などを効率的に分離・除去します。
高い清浄度が得られますが、設備コストやメンテナンス性に注意が必要です。
対策4.環境整備と適切な薬剤使用
1~3に加えて、以下の対策も悪臭抑制に有効です。
工場内の換気
発生してしまった悪臭や、微生物の繁殖を促進する湿気を工場内に滞留させないために、十分な換気を行うことが基本です。
換気扇の能力不足や配置の問題がないかを確認し、必要であれば増強やレイアウト変更、定期的な窓開けなどを検討しましょう。
局所排気装置の設置も有効な場合があります。
機械周辺の日常的な清掃
機械本体やタンク周辺、床、壁などに飛散した切削油剤や切粉、油泥などは、それ自体が悪臭の発生源となり、微生物の侵入経路や温床になります。
日常的に工場内を清掃し、常に清潔な作業環境を保つことを心がけましょう。
殺菌剤・消臭剤の適切な使用
一時的な応急処置として、あるいは他の対策と併用する形で、殺菌剤や消臭剤の使用が検討されることもあります。
しかし、これらの薬剤の使用には注意が必要です。
殺菌剤の効果の持続性、対象となる微生物の種類、使用濃度、油剤との適合性(分離、性能低下、泡立ちなど)、作業者への安全性(皮膚刺激、アレルギー、吸引毒性など)、耐性菌発生のリスクなどを十分に考慮し、必ず切削油剤メーカーの指示や専門家のアドバイスに従って、適切な種類を適切な方法で使用する必要があります。
安易な使用は、かえって問題を複雑化させることもあります。
消臭剤は臭いの原因物質を化学的に分解・中和するもの、悪臭成分を吸着するもの、良い香りでマスキングするものなど様々です。
根本的な悪臭原因を除去するものではないため、あくまで補助的な対策と位置づけ、発生源対策と並行して使用を検討しましょう。
使用する際は、作業環境や人体への安全性を確認し、過度な使用は避けるべきです。
切削油剤が原因となる悪臭の除去方法

万全の対策を講じていても、身体や作業着、工場設備などに切削油剤が原因で発生した悪臭が付着してしまいます。
そんな時に役立つ、具体的な悪臭の除去方法を紹介します。
手や皮膚に付着した悪臭の除去
切削油剤が直接付着した手や皮膚は、まず専用の工業用ハンドクリーナーや油汚れに強い石鹸(スクラブ入りなど)を使用して丁寧に洗い流します。
その後、通常の化粧石鹸やボディソープ(できれば肌に優しい弱酸性のもの)で再度洗い、しっかりとすすぎます。
洗浄後は、肌の油分も一緒に奪われているため、乾燥しやすくなっています。
必ず保湿クリームやローションなどで十分に保湿ケアを行いましょう。
保湿クリームやローションの使用は、悪臭対策だけでなく手荒れ防止の観点からも重要です。
作業着や繊維製品に付着した悪臭の除去
洗濯による悪臭除去
切削油剤が原因で発生した悪臭が染み付いた作業着は、他の衣類とは分けて洗濯するのが基本です。
洗剤としては、油汚れやタンパク質汚れに強いアルカリ性洗剤(例:工業用作業着専用洗剤)や酵素系洗剤が効果的です。
通常の洗濯洗剤に、重曹を大さじ3~4杯(約50g程度)を加えて洗濯すると、消臭効果が高まります。
すすぎの際にクエン酸を少量(水30Lに対し小さじ1杯程度)加えると、アルカリ性の洗剤成分を中和し、臭い残りを軽減する効果が期待できます。
臭いが特にひどい場合の洗濯
切削油剤が原因で発生した悪臭がひどい部分には、洗濯前に液体洗剤や石鹸を直接塗布し、30分~1時間ほど置いてから洗濯すると効果的です。
洗剤を入れた40℃~50℃程度のお湯に、30分~数時間ほど浸け置き洗いをしてから通常の洗濯を行うと、油汚れや臭い成分が落ちやすくなります(ただし、作業着の素材の耐熱性を必ず確認してください)。
乾燥と仕上げによる悪臭除去
洗濯後は風通しの良い場所で、できれば日光に当ててしっかりと自然乾燥させましょう。
紫外線には殺菌・消臭効果も期待できます。
乾燥機を使用する場合は、高温にしすぎると臭いが逆に定着することがあるため注意が必要です。
臭い移りの予防策
具体的な作業着からの臭い移り対策を紹介します。
- 作業着の素材選び:一般的にポリエステル100%の素材は臭いが残りやすく、吸湿性のある綿混紡素材の方が臭いが付きにくいと言われています
- 速やかな洗濯:帰宅後は、できるだけ早く作業着を洗濯機に入れる習慣をつけましょう。放置するほど臭いは落ちにくくなります
- 専用の袋や容器で持ち帰る:臭いの強い作業着は、他の洗濯物と分けて、密閉できるビニール袋や専用のランドリーバッグに入れて持ち帰ると、他の物への臭い移りを防げます
- 重曹水スプレーの活用:緊急用として、水500mLに重曹小さじ1~2杯を溶かした重曹水スプレーを職場に常備し、作業後や休憩中に作業着に軽くスプレーしておくと、臭いの軽減に役立つことがあります
工場設備や床などに付着した悪臭の除去
機械本体や周辺の床、壁などにこびり付いた油汚れが原因で発生する臭いには、アルカリ性の強力洗浄剤や高温の蒸気で汚れを浮かせて除去するスチームクリーナーなどが有効です。
ただし、使用する洗浄剤や清掃方法は、対象となる素材(金属、塗装面、床材など)によっては変色や腐食、損傷を引き起こす可能性があるため、必ず目立たない場所で試してから本格的に使用するようにしてください。
日常的な拭き掃除や定期的な高圧洗浄機による清掃で、臭いの元となる汚れを工場内に蓄積させないことが根本的な対策となります。
工場空間全体の悪臭の対策
工場空間全体の悪臭を除去するためには十分な換気が必要です。
窓や扉の開放、換気扇や送風機の効果的な運用で、常に工場内の空気を入れ替えることを心がけましょう。
活性炭フィルター付きの大型空気清浄機や、業務用の消臭装置(例:オゾン脱臭機、光触媒を利用した装置など)も、空間全体の臭いを軽減するのに役立ちます。
ただし、これらはあくまで発生した臭いに対する対症療法であり、臭いの発生源そのものを断つ対策と並行して行うことが、より効果的な環境改善に繋がります。
切削油剤が原因で発生する悪臭の原因と対策まとめ
切削油剤が原因で発生する悪臭の問題は、1つの対策で解決できるものではありません。
腐敗しにくい優れた切削油剤を選定することを基本とし、その上で日々の適切な油剤管理、効果的なろ過システムの導入、作業環境の清浄化が必要です。
そして、万が一臭いが付着した場合の正しい対処法も必要になってきます。
これら全ての要素を総合的にかつ継続的に取り組んでいくことで、切削油剤が原因で発生する悪臭のない快適で安全な作業環境を実現することができます。
サンワケミカル株式会社の紹介
今回記事を執筆いただいたサンワケミカル株式会社を紹介します。
サンワケミカル株式会社では、高性能な抗菌・防腐タイプの切削油剤「スーパークールANSシリーズ」の提供はもちろんのこと、お客様それぞれの加工内容や設備、お困りの状況に合わせた最適な油剤管理方法を提案しています。
また、専門スタッフによるクーラント交換・タンク清掃サービス、効果的なろ過システムの相談、さらには作業者の皆様への適切な取り扱い方法の講習に至るまで、悪臭問題解決に向けたトータルサポートを行っています。
工場の悪臭でお困りの際は、諦めてしまう前にぜひ一度サンワケミカル株式会社にご相談ください。
サンワケミカル株式会社と共に、品質向上と生産性アップの基盤となる、より良い製造現場づくりを目指しましょう。
編集長コメント
「切削油剤が原因で発生する悪臭の原因と対策」いかがでしたか。
切削加工業界における職場環境の悩みの1つが、切削油剤による悪臭であると認識しています。
切削油剤を変更するだけでなく、それ以外にも対策方法があるため、悪臭に困っている方は本記事を参考にしていただけると嬉しいです。
関連記事
ライター・執筆者情報

本記事は切削油剤メーカーであるサンワケミカル株式会社に執筆いただき、タクミセンパイの服部が編集しました。
私は工具メーカーでの営業とマーケティングの経験を活かし、切削工具と切削加工業界に特化した専門サイト「タクミセンパイ」を2020年から運営しています。
私(服部)の実績や経歴については「運営について」に記載しています。
タクミセンパイとして収集した最新情報をもとに、ここでしか読めない独自視点の記事や調査データを提供しています。
中立的な立場として発信する情報は、読者から「信頼できる」と高い評価を得ています。
メールマガジンのご案内
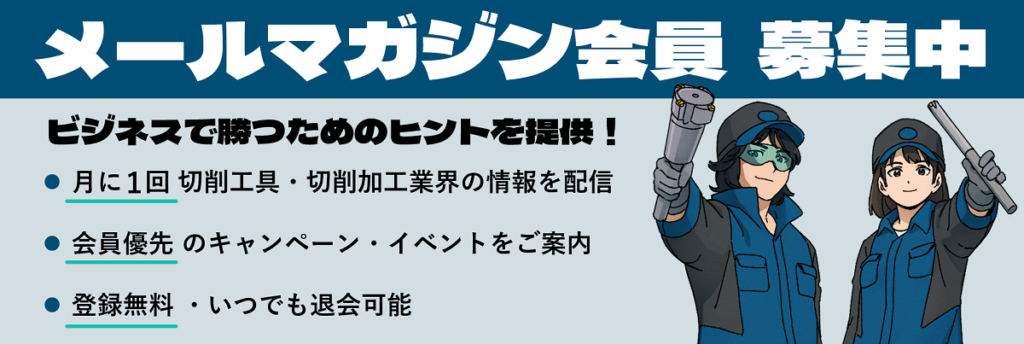
タクミセンパイでは月に1回メールマガジンを配信しております。
お届けする内容としては下記になります。
・切削工具・切削加工業界の新着オリジナル記事
・切削工具・切削加工業界のオススメ記事
・イベント情報
・会員優先のキャンペーン・イベント情報
ご興味のある方は「メールマガジンのご案内」ページをご確認ください。
会員登録は無料でいつでも退会可能です。

