
製造業系の展示会に初めて参加する際、事前準備・回り方の参考となる情報を知りたいと困っていませんか。
この記事は切削加工の技術広場 キンタンに記事執筆を依頼し、切削工具と切削加工業界に特化した専門サイト「タクミセンパイ」が編集しました。
本記事では製造業系展示会の視察を成功させる方法についてまとめています。
この記事を読むことで、製造業展示会において視察の目的を達成するだけでなく、満足度の高い成果を得ることができます。
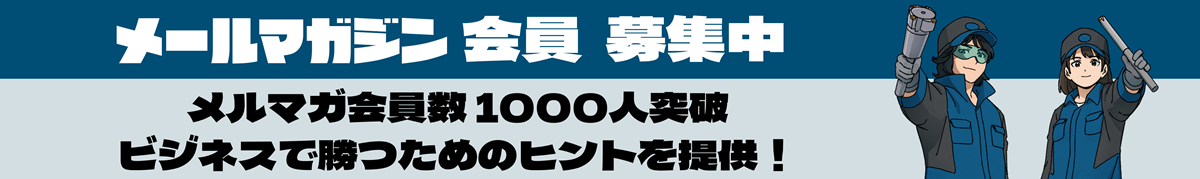
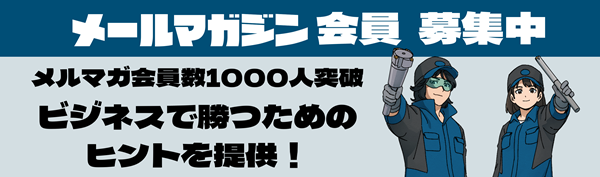
製造業系展示会の視察を成功させる方法
「切削加工の技術広場 キンタン」では、製造業系展示会で取材した企業ブースをXやInstagramで紹介する情報発信活動をしています。
Xの投稿を一部紹介させていただきます。
本記事では、製造業系展示会を取材しているキンタン高橋が、キンタン流「製造業系展示会の視察を成功させる方法」として下記の展示会視察のポイントを紹介しています。
- 展示会が持つポジティブな面とネガティブな感想
- 展示会は釣りと似ている!?
- 展示会で情報のヒット率を上げる方法
- 開催期間中のいつ展示会に行くべきか
- 展示会当日の心構え
- 展示会で声をかける時に緊張してしまうあなたへ
展示会が持つポジティブな面とネガティブな感想
まずは展示会のポジティブな面とネガティブな感想を紹介したいと思います。
展示会は生で実機に「見て」「触れて」「疑問をその場で訊く」ことができます。
そのため、カタログだけでは気付けなかったことや、生で触れたからこそ湧いてくる課題解決へのインスピレーション・イマジネーションを得ることができ、展示会はタイパの面でも優れていると思います。
これは展示会のポジティブな面の1つといえるでしょう。
一方で、 展示会が「思っていたのと違った」という感想も大事な収穫です。
展示会はポジティブなイメージだけがあるわけではありません。
「展示会がどれも同じに見えてつまらない」「行ったことがある展示会にまた参加する気になれない」「自分の発見につながるまわり方がわからない」「どのように会場をまわると効率的かわかない」「ずばり展示会が苦手」などネガティブな感想を持っている方もいると思います。
この記事が少しでもあなたの展示会視察の参考になれば幸いです。
展示会は釣りと似ている!?

展示会は大原則として「行ってみなければわからない」という絶対的な特性を踏まえて本記事を説明していきます。
「釣りは狙ったものが確実に釣れるから面白い!」と思われてしまうと、多くの人に釣りの魅力を説明するのが困難になると思います。
展示会も一緒で、「行けば必ず狙ったものが得られる!」と思ってしまうと、それこそせっかくの魚(出会い)が逃げていきます。
「収穫が乏しかった」や「自分に合わなかった」などネガティブな感想で終わる展示会は、言い換えると「期待値を下回った」ということです。
そのため、期待値とは何だったのかを自己分析することで展示会の捉え方が変わると思います。
展示会の帰り道に「来てよかったな」と思うには、満足ポイントである「情報のヒット率」を上げることが大事です。
「一体自分は展示会に何を期待していたのか」という期待値を分析し、コントロールすることで「情報のヒット率」を上げることができます。
展示会で情報のヒット率を上げる方法
展示会で「チェックしたいモノ&コト」のどちらかがあるだけで、情報のヒット率が上がります。
「チェックしたいモノ&コト」という獲物の大きさがわかった上で展示会という海に釣り糸を垂らしたことになるため、釣れた時は嬉しいものです。
ゲットした獲物(情報)を元にして、その情報の量や質を上げる最適な方法があります。
それは「比べる」ことです。
展示会では生で実機を比べることができる最高の環境が提供されています。
カタログで見比べるより実機での比較です。
生の情報に触れて比べるだけでその情報は輝きを増します。
展示会場で生の情報に触れることで、あなたの脳内にある収穫BOXにいくつかの魚影が想像できると思います。
これはとても基本的な確率の上げ方です。
「チェックしたいモノ&コト」と言われて浮かぶものがあっても、それが本当に大事なものか自信がないと考える方もいるかも知れません。
「チェックしたいモノ&コト」を選ぶコツは1番知りたいことでなくても大丈夫です。
2番目や3番目に知りたいことでも問題ありません。
さらに、この記事を読まれている皆さん忙しいと思います。
そして、展示会が3度の飯より好きなわけでもないと思います。
そんな皆さまは、展示会の事前準備に時間とエネルギーを使えないことがほとんどだと思います。
そのため、本当に展示会場でチェックしたいものかどうかを推し量るのではなく、「チェックしたいモノ&コト」を決めることが大事です。
それが展示会場でインスピレーションやイマジネーションが湧くスイッチになると信じましょう。
展示会視察において感覚はとても大事なことですが、私は「半感覚」「半調べ」が大事だと思っています。
展示会特設サイトの確認ポイント
展示会の特設サイトを鼻歌まじりでササァーっと閲覧することが大事です。
好きな1曲分(3~5分)の時間でも閲覧として十分な効果があります。
展示会特設サイトは以下の3つを意識して確認することで効率が上がります。
- キャッチコピー
- 出展規模(出展企業数や会場の広さ)
- 会場MAP(出展メーカーのチェックでもOK)
「キャッチコピー」とは特設サイトを開いてまず目に飛び込む、この展示会の魅力をわかりやすく表現したメッセージのことです。
「世界最大級のAM技術の祭典」や「製造業DXやAIの最新活用を知る!」などのことです。
そこに補足するように特徴が書いてあるので、まずはこの展示会のユニークさを頭に入れます。
次に「出展規模(出展企業数や会場の広さ)」について、展示会規模は「情報のヒット率」という目的に影響するので大事な情報になります。
展示会規模に「滞在時間」をかけることによって「情報のヒット率」が変わるのであれば、それに見合った考え方が必要です。
どのくらいの時間滞在するかは、釣りで例えるなら「どれくらいの時間釣り糸を垂らすか」です。
滞在時間が、釣れる魚の量(情報量)に影響することは容易に想像できます。
そのため、あくまで滞在時間の中で「情報のヒット率」を上げるというゲーム性は忘れてはいけません。
そこで会場MAPの存在が大事になります。
RPGで例えるなら「チェックしたいモノ&コト」とはイベントです。
展示会に参加できる制限時間が決められているのであれば、やはり効率的にクリアするゲーム性を意識すべきかと思います。
まとめると「キャッチコピー」で展示会の特徴(ユニークさ)を知り、「出展規模」を知った上で自分の滞在時間を意識し、「会場MAP」で時間内にチェックするブースをなんとなく確認しておくことです。
ちなみに「会場MAP」のチェックは規模が大きい場合、正直そこまで時間やエネルギーをつぎ込めないと思います。
そのため、当日の会場エントランスでチェックしても良いと思います。
私は前日にどんな企業が出展しているかをざっとチェックしたら、当日会場エントランスで赤ペン片手に会場MAPに寄りたいブースを片っ端から赤丸を入れ、会場のムード(人混みや雰囲気)を感じながらまわる経路を考えます。
10分、長くても15分でチェックすることができますので、そこまでオーバーな時間投資になりません。
さあ、入場許可証の登録を終えたらいよいよ当日を迎えますよ!
開催期間中のいつ展示会に行くべきか

展示会の期間は3日間、曜日としては水曜日〜金曜日に開催されることが多いです。
もし参加日を選べるとすればいつ展示会に行くのがいいと思いますか。
展示会の各日程に特徴があるのでメリット・デメリットを紹介します。
展示会初日(1日目)
展示会初日(1日目)のメリットはズバリ「出展ブースの説明員さんがみんな元気」ということです。
説明員さんが元気であるため、積極的に質問に答えてくれます。
次に展示会初日の混雑具合ですが、平日ど真ん中ということもあり開催期間中で一番空いています。
展示会初日は説明員さんが元気であり、人があまりいない状況で丁寧に教えてもらえることに加えて、担当者に気兼ねなく質問できることも大事なポイントです。
混雑に紛れることなくブース内をスムーズに見学できるので、情報獲得量が上がります。
展示会で初公開される技術や製品がある場合は、混雑に紛れることもなく説明員さんに質問できるのはメリットだと思います。
展示会初日のデメリットは説明員さんがまだスタートしたばかりで説明に慣れていないことです。
説明員さんも緊張しているため、たどたどしく説明されることもあります。
それが分かった上で、こちらもきちんと丁寧に質問することが大事になってきます。
他には、初日を終えて翌日SNSで展示会に関する投稿を見ると「え!?そんなんあったん!?」という情報が入ってきて「…見たかったな…」と膝から地面に崩れる経験をすることです。
展示会最終日
展示会最終日は初日と異なり、SNSなどで情報が出てから参加することができるため、取りこぼしが少なくなります。
また、出展ブースの説明員さんの説明スキルが上がっていることもポイントです。
「こうすれば相手に伝わるんだ」という説明の仕方を発見している説明員さんにあたると気持ちいいくらいスッと理解できます。
展示会最終日のデメリットはやはり混雑です。
人が多いと説明員さんの取り合いになってしまい、せっかく聞きたかったことも「いいや」と思ってしまいます。
スムーズに見学できないことや、実機をゆっくり見学したい場合も人が多いと視察しづらくなります。
展示会初日・最終日以外の日程
展示会初日・最終日以外の日程は、メリットもデメリットもまさに平均といった感じです。
展示会当日の心構え

いよいよ展示会場の入口に立ちました。
では、さっそく自分で決めた展示会の「チェックしたいモノ&コト」をゲットするため、目的の場所へ向かいましょう。
可能な限りすぐに展示会視察の目的を果たすことを意識にしてください。
それは、自分の興味があることから展示会視察を始めると良いことがあるからです。
知らなかったことを知るという展示会視察における最高の武器(発見)をゲットできる可能性があります。
「え!?そうなの!!」という展示会での喜び・発見は、まさにRPGであればレベルが上がる音が聞こえてくるようなイベントです。
キンタンで大事にしている言葉として「発見とは誰かにとって大したことないことでも自分にとっては宝物」があります。
余談ですがキンタンの名前の由来は金属探知を略して金(キン)探(タン)で、あなたにとって宝物のような発見をして欲しいという思いで付けました。(さらっと宣伝してすみません)
「え!?そうなの!!」「あ!そうなんだ!」という発見を展示会場でした瞬間から、それまでの「チェックしたいモノ&コト」は少し進化していることでしょう。
宝さがしは「ここに宝があるかも!」と思って冒険に出るからこそ見つけられるもので、そうでなければせっかくの宝も見落としてしまいます。
そのため、なるべく早く視察目的の企業ブースに向かった方がいいです。
「思っていたのと違ったな」を早く気付くことも、時間制限のある展示会を効率的にまわることにつながります。
また、展示会が思っていたのと違うと感じたとしても、得た情報を持って「他と比べる」ことで、違う角度からの認知を深めて新たな化学反応を生み出すことができます。
展示会では「好きなものをあとにとっておく」のではなく、「すぐゲットする」ことが視察当日の情報密度やドラマを良いものに変えるチカラになります。
展示会場をまわるコツ

展示会で広く浅くいろいろ見たいという方もいると思います。
つまり展示会全体の市場調査やトレンド、業界の動向をチェックしたい場合です。
例えば、初めて参加する展示会は勝手がわかりにくい場合があると思います。
自分の仕事とイメージが直結しにくい、例えばDXやAIといった仕事効率系の展示会などがわかりやすいでしょうか。
このような初めて参加する展示会の場合でも、まずはこれまでに紹介したような「情報のヒット率」を上げる方法を半感覚・半調べで参加することをオススメしますが、加えて情報獲得率を上げるコツがあります。
それは、最初に早歩きで展示会場をまわることです。
くまなく見る必要はないのですが、ザっと会場内にどのようなブースがあるのかを理解できるぐらいは早歩きでチェックします。
最初に早歩きで展示会場をまわるのとまわらないのでは、情報獲得率がかなり違ってきます。
会場入口から目についたブースを見ていくと、滞在時間内で見れなかったエリアが多かったといった経験や、帰らなければならない頃に興味深いブースが立ち並ぶエリアに足を踏み入れたり、出口ゲートに向かっている最中に気になるブースを横目に帰ったりした経験はありませんか。
展示会で「気になる」というのは、あなたが求めているもの、あなたに適した栄養素(情報)に向かって動物的カンが働いたということです。
そのようなカンは展示会視察で大事です。
カンを元に視察した企業が結果として有益ではなかったとしても、あなたにとっては大事なチェックだと思います。
会場を早歩きでザっと見てどこにどのようなものがあったのかという確認は、市場調査やトレンド調査、または学びのキッカケを求めている場合にとても有効的で情報獲得率が格段に上がります。
「チェックしたいモノ&コト」を中心にブースをめぐることを「点」とするなら、全体的な市場調査やトレンド調査は「面」で捉える展示会といえるかも知れません。
どちらも準備して展示会に参加すると、視察によって得た情報の整理がしやすくなります。
展示会で声をかける時に緊張してしまうあなたへ
展示会場で説明員さんに声をかけるってすっごくドキドキしませんか。
私は取材に行く前、よく震えています。
唾を飲んで、呼吸が浅くなって、それを深呼吸で整えて、えい!っとブースに向かって突進して、やっぱりビビって早足で通り過ぎたりするなんてしょっちゅうあります。
この緊張をなくせるコツがあるかはわかりません。
ただ、いつも思うようにしているのが、展示会場の説明員さんだってドキドキしているだろうということです。
「自分の説明が相手に届くだろうか…」というのは、ほとんどの説明員さんが思っているのではないでしょうか。
もし自分だったら「何だか試されてるようで怖いな…」と考えてしまいます。
なので、説明員さんが緊張しないように接するということは大事なことだと思います。
その上で、説明員さんの説明に「いま私はこう理解しましたが合っていますか?」という確認を入れるように心がけています。
確認を入れることで、説明員さんの説明の精度が上がり、そして楽になるのではと思うからです。
説明員さんに丁寧に接したとしても、言葉のすれ違いは発生しますし、人と人の相性もあります。
そのため、そこまで気にしすぎることなく、展示会の一期一会を楽しむことをオススメします!
最後に&キンタンの紹介
ここまで長い文章を読んでいただきありがとうございました。
キンタンが紹介した「製造業系展示会の視察を成功させる方法」はいかがでしたか。
少しでも皆さんの展示会視察の役に立てたら嬉しいです。
正直まだまだ書きたいことがありました。
またどこかでご紹介できたらと思っています。
キンタンは切削加工業や製造業の「企業」や「個人」の得意を発信し発見をするWEBサイトです。
展示会情報を調べたり、注目の商品や知識・情報を発見したり、キンタンを通して発信することもできます!
詳しくは「切削加工の技術広場 キンタン」のWEBサイトをご覧ください。
また、キンタンではこれから開催される展示会スケジュールを「展示会・イベント情報」で公開し、X・Instagram・noteで発信していますのでご覧ください。
編集長コメント
「製造業系展示会の視察を成功させる方法」いかがでしたか。
製造業に関連した展示会は全国で多数開催されていますが、初めて参加する方は事前準備・回り方の参考となる情報を探されているのではないでしょうか。
展示会に参加して積極的にSNSで発信されているキンタン高橋様にキンタン流「製造業系展示会の視察を成功させる方法」を教えていただきましたので、参考にしていただければと思います。
初めて参加する展示会は不安もありますが、それ以上に刺激があるため、タクミセンパイとしても展示視察を学びに活かすことをオススメしています。
関連記事
ライター・執筆者情報

本記事は切削加工の技術広場 キンタンの高橋様に執筆いただき、タクミセンパイの服部が編集しました。
私は工具メーカーでの営業とマーケティングの経験を活かし、切削工具と切削加工業界に特化した専門サイト「タクミセンパイ」を2020年から運営しています。
私(服部)の実績や経歴については「運営について」に記載しています。
タクミセンパイとして収集した最新情報をもとに、ここでしか読めない独自視点の記事や調査データを提供しています。
中立的な立場として発信する情報は、読者から「信頼できる」と高い評価を得ています。
メールマガジンのご案内
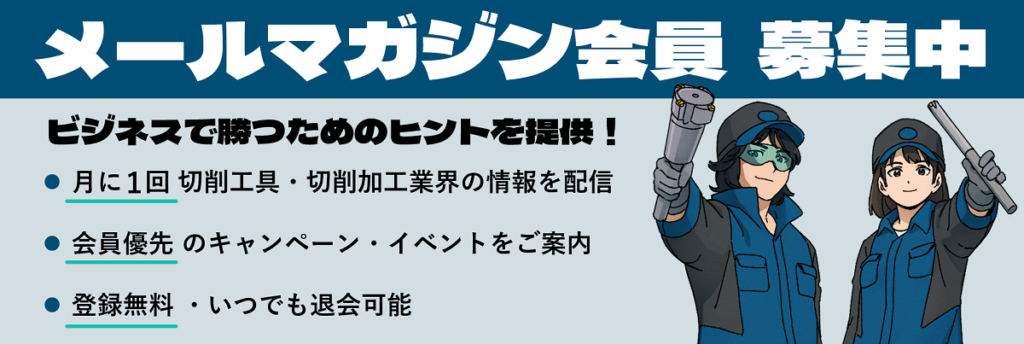
タクミセンパイでは月に1回メールマガジンを配信しております。
お届けする内容としては下記になります。
・切削工具・切削加工業界の新着オリジナル記事
・切削工具・切削加工業界のオススメ記事
・イベント情報
・会員優先のキャンペーン・イベント情報
ご興味のある方は「メールマガジンのご案内」ページをご確認ください。
会員登録は無料でいつでも退会可能です。

